形状のみの意匠の利用に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
形状のみの意匠の利用 – 倭猿
2009/05/30 (Sat) 09:44:07
質問です
先願登録意匠A:形状のみ
後願登録意匠B:形状+模様
AとBは非類似
問題文では特別事情の記載なし。
以上の事案で、BはAを利用すると書くべきでしょうか?
Re: 形状のみの意匠の利用 – 管理人
2009/05/30 (Sat) 23:26:43
倭猿さん
ご質問ありがとうございます。
幣サイトのレジュメ要約集をお持ちの場合は、意匠法2条の解説をご覧ください。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
先願登録意匠が形状のみの意匠であり、後願登録意匠がそれに模様や色彩を結合した意匠である場合、利用関係が成立すると解します(意26条)。
後願登録意匠を実施すると先願登録意匠を全部実施するが、その逆は成立しないからです。
但し、後願登録意匠において、形状と模様又は色彩とが渾然一体となっている場合、利用関係は生じないと解します。
先願の形状のみの意匠をそっくりそのまま後願の登録意匠等に取り入れているとはいえないからです。
Re: 形状のみの意匠の利用 – 倭猿
2009/06/01 (Mon) 08:23:02
管理人様
ありがとうございます。
>後願登録意匠を実施すると先願登録意匠を全部実施するが、その逆は成立しないからです。
このように定義しますと、AとBは非類似であるため、後願登録意匠を実施しても先願登録意匠を実施することにならないのです。
よって、利用関係は成立しないとも書けるのではないでしょうか?
まぁ、形状のみ意匠に限らず、部品と完成品でも、物品非類似だからこのような疑問はあったのですが、形状のみの場合特に違和感を感じました。
処理の方法としては、
「形状が同一にもかかわらず非類似」→「渾然一体」
と認定して利用関係を否定するのが妥当でしょうか?
Re: 形状のみの意匠の利用 – 管理人
2009/06/01 (Mon) 12:20:10
>AとBは非類似であるため、後願登録意匠を実施しても先願登録意匠を実施することにならないのです。
よって、利用関係は成立しないとも書けるのではないでしょうか?
確かに、「実施」の文言が誤解を招く場合もあります。
この場合は、「先願の形状のみの意匠をそっくりそのまま後願の登録意匠に取り入れているからである。」というのはいかがでしょうか?
いずれにしても、この事例の場合に利用関係「非」成立というのは、妥当ではないと思います。
>「形状が同一にもかかわらず非類似」→「渾然一体」と認定して利用関係を否定するのが妥当でしょうか?
これは別問題ですね。
渾然一体以外で、「形状が同一にもかかわらず非類似」という意匠も想定されるので、上記条件のみで「渾然一体」と認定するのは危険です。
なお、渾然一体の場合は、「形状と模様又は色彩とが渾然一体となっている場合は、先願の形状のみの意匠をそっくりそのまま後願の登録意匠等に取り入れているとはいえないので、利用関係は生じないと解する。」となります。
Re: 形状のみの意匠の利用 – 倭猿
2009/06/01 (Mon) 15:41:47
管理人様
ありがとうございます。
すいません。ちょっと教えていただきたいのですが、
>>確かに、「実施」の文言が誤解を招く場合もあります。
利用の定義の「実施」は、2条3項の実施のことですよね?
AとBが非類似であるにも拘らず、「Bを実施すればAを実施したことになるから利用成立」と書くのは論理矛盾を生じさせないでしょうか?
あと、
>>「先願の形状のみの意匠をそっくりそのまま後願の登録意匠に取り入れているからである。」
この理由づけ、ありがとうございます。
この理由づけは、一般的な利用の定義を書かずに使用するもの、と考えてよろしいでしょうか?
Re: 形状のみの意匠の利用 – 管理人
2009/06/02 (Tue) 12:48:09
>利用の定義の「実施」は、2条3項の実施のことですよね?
AとBが非類似であるにも拘らず、「Bを実施すればAを実施したことになるから利用成立」と書くのは論理矛盾を生じさせないでしょうか?
正直、分かりません。
ただし、青本でも自転車とハンドルの例において、「実施」の言葉を使っているので、部品を含む完成品の実施は、当該部品の実施にもあたるという解釈なのでしょうか?
>この理由づけは、一般的な利用の定義を書かずに使用するもの、と考えてよろしいでしょうか?
利用の定義で使用できますが、正確には、「意匠の本質的特徴を損なうことなく、先願意匠を後願意匠の中にそっくり取り入れること」だったと思います。
そっくり説(意匠法概説?)で調べてみてください。
↓弁理士ブログの順位はコチラで確認できます↓
![]() (本日4位) (本日1位)
(本日4位) (本日1位)
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら
形状のみの意匠の利用
 ブログ
ブログ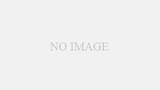
コメント