!ネタバレ注意!※ネタバレを含みますので、未見の方はTverでドラマをご覧になってからお読み下さい。
5/17放送の「それってパクリじゃないですか?」第6話は、学会発表と官能試験がテーマでした。この第6話では、ドラマ関係者の業界調査がかなり正確に行われたことが伺えて、非常に感心させられました。というわけで、今回も専門家として、初学者にもわかりやすいよう条文を交えて説明していこうと思います。
新規性喪失の例外とは? –特許法第30条–
特許権は、所定期間(原則的に出願から20年)、発明の実施を独占できる権利です。そのため、発明が特許として登録されるためには、いくつかの条件があります。その条件の一つが、「新規性(新しいこと)※特許法第29条1項3号 」であり、既に第三者に知られてた発明(例えば、公表された発明)は、特許として登録されません。しかし、発明をなるべく早く公表したいと考える発明者もいるので、例外的に、発明が公開された後に特許出願しても、新規性が喪失しないものとして取り扱う制度が設けられており、これが「新規性喪失の例外」です。
ただし、作中でも説明されていたように、新規性喪失の例外が適用されても、発明の公表から出願までに間に他人が出願してしまった場合には、特許として登録されません。実際、学会発表から着想を得た発明を出願して、それが登録されるという事例も少なからず存在します。そのため、実務上は、新規性喪失の例外は、極力使用を避けるべき制度とされています。また、新規性喪失の例外を使用する場合、出願と同時に、発明の新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出しなければなりません。さらに、第三者に知られた場合に新規性を喪失するので、例えば、開発部の同僚、弁理士、又は守秘義務を負っている者に知られても新規性は喪失しません。
なお、新規性喪失の例外は、比較的に長い用語であるので、業界では「新喪例(しんそうれい)」と略称されているそうです(私は最近知りました)。そのため、「しんそうれいを使います」とか言うと、業界人っぽくなるのではないでしょうか?
学会発表と特許出願
ドラマの設定にある通り、学会発表をしてしまうと発明を知られてしまい特許を登録できなくなりますので、特許出願は、学会発表前に行います。もしくは、発明の肝となる部分を伏せて発表してもらいます。通常、学会発表の内容(要旨)は事前に決められており、学会開催前に主催者へ要旨を提出します。その後、提出した要旨は、要旨集等の形で公開・配布されます。そのため、厳密には、要旨の提出前に特許出願をすべきと言えます。ただし、学会の主催者は、一般に守秘義務を負っていることが多く、実際には要旨集の公開・配布前であれば新規性を喪失しません。
なお、ドラマの設定では特許出願(要旨提出)までの猶予が2週間とされていました。しかし、2週間という期間は、出願準備期間として考えれば、「対応できない」というほど短い期間ではありません。この点、ドラマの中では、「期間が短いために出願できない」という理由ではなく、「データが足りないから出願できない」という理由になっていました。正直、実務的にあり得る理由を選択している点に、非常に感心しました。また、データが足りないことが拒絶理由に当たるというのは、第5話で説明されているので、構成上も不自然さがなかったですね。
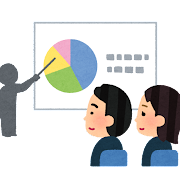
共同開発契約と職務発明 –特許法第35条–
ドラマの中では、大学と月夜野ドリンクとの間で共同開発契約が交わされていました。このように、大学との共同開発では、共同開発申請書を提出して共同開発契約を締結するのが一般的です。また、ドラマでは、研究室の教授が「秘密保持義務」について知らなかった・忘れていたという風に描かれていました。近年では、発表前の特許出願が周知されているので、知らないというのは考え難いのですが、教授が契約書を読んでいないという可能性はあります。
例えば、企業の従業者が発明をした場合、特許出願を行うのは発明者ではなく企業になることが多いです。そのため、このような発明は「職務発明」と呼ばれ、あらかじめ企業が特許出願できるように対処されてます(特許を受ける権利が会社に譲渡されている)。具体的には、従業者等がした発明が職務発明である場合には、あらかじめ、企業等に特許を受ける権利を取得させることを契約等で定めるたとしても、無効とはされないとされています(特許法第35条第2項)。
大学も同様であり、特許出願を行うのは大学であって(企業と共同で出願する場合には大学と企業)、発明者ではありません。そのため、共同開発契約も大学と企業とが締結します。そして、契約の当事者ではない教授(及び発明者としての学生)が、契約締結に関わらなくとも契約は締結されます。この場合には、教授が契約書を読んでいないという可能性はあります。
官能評価とは?
官能評価とは、人間の五感である味覚、嗅覚、視覚、聴覚、及び触覚を利用した評価のことです。味(美味しい)や匂い(臭い)などは、科学的な試験によって評価することが難しい場合があります。一方、発明の効果が、味や匂いの向上であるということがあります。この場合であっても、特許の出願書類には、発明によって課題を解決できる(十分な効果を発揮できる)と認識できる程度の記載が必要です(この点も第5話で説明されているので、 ドラマの構成に感心します)。そのため、官能評価を行って、十分な効果を発揮できることを出願書類(明細書)に記載します。
ただし、ドラマでは「曖昧」と表現されていたように、官能評価は人間の主観によるところが大きいです。そのため、主観を排除するために、試験方法に慎重な配慮が必要とされます。一例として、トマトジュース事件という判決(平成28年(行ケ)10147号)があります。この事件では、官能評価の方法が問題となり、特許が無効とされました。具体的に判決では、飲食品の風味には、甘味、酸味以外の様々な他の要素が影響を及ぼすので、評価試験(官能評価)をするに当たっては、他の要素を一定にした条件で評価試験をすべきである等と判断されました。そして、そのような条件がない出願書類の記載から、発明と得られる効果との関係の技術的な意味を理解できるとはいえないとして、特許無効という判断がされています。

官能評価にはこのような難しさがあり、簡単に実施できるものではないため、慎重な取り扱いが必要となります。なお、官能評価ではありませんが、機械的な性質を評価・試験する場合も慎重な取り扱いが必要な点は同様です。そのため、ドラマとは違うのですが、官能評価自体は、「曖昧」と断定されるような手法ではないといえます。





コメント